|
 |

(写真A) |
| |
|
2011年12月購入。
2008年に
川崎の山野楽器ギタースポット店が開店何周年かの記念特別企画として、
Fender Custom Shop のマスター・ビルダーDennis Galuszkaに発注した一本。
【貴重な材、特別な材を使ってのスペシャル・バージョンのPrecision Bass】
という企画だったのであろう。
スポルテッド・フレーム・メイプルのトップはなかなかの存在感。
ボディーやネックも良い材を使っている。
2010年の末頃からだったろうか、山野楽器サウンドクルー吉祥寺店に移され展示されていた。
 |
(写真B)
スポルテッド・フレーム・メイプルのボディー・トップはFender製のベースとしては珍しい。
(改造前のオリジナル状態の写真) |
実はこのベースのピックアップの位置は、通常のPrecision Bass のポジションではないのだ。
普通より5mm強ブリッジ寄りに付いている。
そのため、所謂Precision Bass の音ではない。
あのぶっ太い音より、ほんの少しモダンな音が出る。
Fodera Anthoney Jackson Presentation 6-string Contrabass Guitar のピックアップと
ほぼ同じ位置にある。
ナチュラル・ハーモニックスがよく出る。
ちょっと硬質な、Precisionらしからぬ音も出せる。
アビゲイル・イバラ女史の手巻きピックアップは、やはり出音に艶と存在感がある。
バダスⅡブリッジも独特なリミッター感を出す。
しかもネックは22フレット仕様。
何やらネックが普通のPrecision Bassより長い気がした。
このベースのちょっと不思議な出音は、見た目のユニークさと似合っている様な気がした。
やはり何と言っても木目の美しさが目を引く。
そんな訳で、ちょっと気になるベースであった。
 |
(写真C)
ヘッドのトップもボディー・トップと同じ
スポイルド・フレーム・メイプル |
 |
(写真D)
デニス・ガルスカの刻印。
ネックは目の詰まった良い材を使っている。
ペグはヒップショット製の軽量タイプ。 |
マスター・ビルダーのデニス・ガルスカへの特注品で、プライム・ウッドを使っている記念作品、
という事で店頭販売価格は、ただでさえ高いマスター・ビルダー物の中でもビックリするくらいに高かった。
そして普通のPrecision Bass とは違った出音。
所謂Precision Bass弾きが求める音ではない。
そのせいであろうか、ずっと売れずにいた。
2011年3月11日
東日本を大震災が襲った。
東京も凄い揺れであった。
店の楽器たちも被害を被った。
壁の高い位置に吊り下げられていたこの一本は、特に酷い目にあった。
激しく揺れて隣り同士ぶつかった挙げ句に、約1.5m 程下の床に落下したのだ。
幸いネックは無事だったが、ボディーには深い傷痕が残ってしまった。
 |
(写真E)
落下によって深い傷がついた |
 |
(写真F)
落下の途中で何かの金具に激しく当たり、こそげ落ちた痕 |
私は震災後に店に行ったときに、被害を受けた楽器たちがどんな音になってしまったかに興味を持ち、
前から気になっていた個体を一本一本弾いてみた。
その中でも、この一本の無惨な傷痕は印象的だった。
しかし、音は変っていなかった。
ユニークなしっかりした出音に、妙に心惹かれるものを感じた。
幸いな事に傷はボディー内部には及んでいなかったのだ。
目の詰まった良い材を使っていたお蔭であろうか。
とはいえ、売り物とは言えない状態だった。
2011年12月
大震災から9ヶ月。
このベースは既に売り物としては展示されていなかった。
頼んで倉庫から出してもらい、久々に弾いてみるとやはり面白いベースだと思った。
どうしてもこのベースには惹かれる魅力がある。
買う事にした。
大きなダメージを負ったベースなので、先ずは日本を代表する名リペアマンのF氏に、
診断と調整を頼んだ。
ところが、である。
このベースを詳しくチェックしてもらってみると、大震災の被害以前のとんでもない問題が発覚したのだ。

ブリッジ・プレートを取り外してみるとその下には、間違えて開けたブリッジ取り付けのネジ穴をふさぎ、開け直した跡があった。

ネックポケットの奥に削り残しの段差がある。ネック取り付けのための5本のネジに対して6個の穴。
発見された異常な点は
●ブリッジ取り付けのネジ穴を間違えて開け、それをふさぎ、更に開け直した跡がある。
●ネックポケットの奥に削り残しの段差がある。
●ネック取り付けのための5本のネジに対して6個の穴が開けてある。
これはいったいどうした訳であろうか。
推察するに、
指定された木目のスポルテッド・フレーム・メイプルをトップに貼付けたカスタム・ボディーを、通常のPrecision の型に従ってカッティング。
通常のPrecision Bassの位置にピックアップのザグリを彫り、ブリッジ取り付けネジの穴を開け、ネックポケットも彫った。
しかし取り付けるネックが22フレット仕様という注文だった事に、後で気づいた。
実はカスタムやデラックス・モデルは通常21フレット仕様が多い。
(ノーマル仕様は20フレット)
22フレット仕様だと当然ブリッジ位置をネック寄りに移動させないとオクターブが合わない。
既に穴を開けてしまっていたが、貴重で高価なトップ材(たぶん木目の位置も指定)を使ってしまっているため、ボディーを無駄には出来ない。
木目を見せるためにピックガードは無しの注文だから、ピックアップのザグリが丸見えになる。
だから今更ザグリ位置を変えるわけにはいかない。
仕方なくそのまま製作を続ける。
ブリッジの位置をネック寄りにする為にネジ穴を開け直し、元の穴を埋めた。
ネック取り付けのポケットも深く彫った。
(ポケットの奥に削り残された段差は、ネックの仕込み角度を変えるためのものだったのであろうか…)
ネック取り付けネジの穴も変更した。
素人の勝手な想像で、作り手に対して失礼かもしれないが、
「高価な材の、指定の木目の部位を使っていたがためにやり直しがきかない」
という事だったのではないかと思った。
実際のところ、他のPrecision Bassより全長が長い。
ボディーは同じ長さだが、ネックがハイポジション22フレットの1フレット分長い。
丁度ブリッジのネジ穴の変更分だけ狂いが生じている。
どうやら想像通りか…
或いは発注の段階で通常のボディー加工(予算の都合上)の上に、22フレットのネックを付ける注文だったか…
何れにしても【22フレット仕様】というところに謎を解く鍵がありそうだ。
まあそんな事をとやかく言っても仕方ない。
このベースは我が家の一員になった訳だから。
私自身が魅力を感じて買ったのだから。
さて、
F氏の手により、ネックポケットの削り残しは綺麗に整地し
、
ネックも安定する様に細工した。
いつものPrecision Bassより長目のネックは、ちょっと不思議な弾き心地。
しかしスラップが歯切れ良く決まり、妙にやり易い。
ピックアップの位置がブリッジ寄りのために、ドシンとした所謂PBの音ではないが、
クリアで伸びのある独特の出音である。
2012年6月
この変わり者のベースを、いっその事に更に個性的な物にしようと思い立ち、
F氏に頼んでJazz Bass のピックアップ(C.S.のヴィンテージ・タイプに手を加えたスペシャル・バージョン)を増設した。

'62年製のJazz Bass と同じ位置にピックアップを増設。
元々Pピックアップが少しブリッジ寄りなために、'62年製Jazz Bass と同じ位置にJJピックアップが取り付けられる。
フロントJ とセンターP の間隔が無いため、フロントJ の取り付けビスを一個カットして三個のビスで支持。
フロントJ 専用のボチューム・ノブを増設。
元々のマスターボリュームは、センターPとリアJの二つのマスター・ボリュームにした。
そしてマスタートーン・ノブとの間の位置に、
センターP/PJミックス/リアJ の、3ポジションのピックアップ切替えスイッチを増設。

各ピックアップ単独の音は
● フロントJ:少し出力は小さいがヴィンテージの'62年製Jazz Bassフロントの音
● センターP:中域の輪郭がハッキリとした元気な音
● リアJ:中域の輪郭がハッキリとしたJaco的な音
ミックスすると
◎ フロントJ+リアJ
とても'62年製Jazz Bass的でありながら、ボディーがPrecisionなので微妙に違う響きもある。
このピックアップは個体として、とてもJaco的でなかなか良い。
特にリアJ は歯切れが良いのでリズムが際立つし、伸びも有るためによく歌える。
◎P+リアJ
所謂 PJ だが、両ピックアップの位置が近いので、
コロコロとしていながらシャキッとした音だ。
ちょっとAlembicのリア寄りのミックスの様な個性的な出音。
トーン全開でコーラス・エフェクターをかけるとアルペジオが綺麗に決まる。
エフェクターの乗りが良い。
トーンをしぼると、ポップで弾みのある音になる。
これは面白い。
◎フロントJ+P
Precision Bass をクッキリとさせた様な、それでいて太い、
存在感があるが優しい音。
◎ J+P+J
Jazz Bass の輪郭をハッキリさせて、しかも太くした音。
これがどうして、なかなかいける。
実にナイス。
このベースならではの音だと言える。
という訳で、
とにかく、普通ではない(普通の音も出るが)、実に個性的で面白いベースになった。
そして鳴りが良い。
何やら不思議な間違いだらけの個体ではあるが、
流石はマスタービルダー、デニス・ガルスカの腕。
楽器としてはしっかりした基本を持っているのであろう。
そして何と言ってもやっぱり、F氏の調整の腕が冴えている。
すぐに作曲とデモ録音に使い、ライブでも活躍。

(写真撮影:梛野浩昭氏 2012年12月1日吉祥寺サムタイムにて)
弾き易いし、音も良いし、ベース好きなお客様からの評価も高い。
様々な音が使えて便利なので、地方に長期滞在の時などもよく連れて行く。
ドバイ旅行にも連れて行った。
作曲・デモ録音の時にとても便利である。

このベースの本当の魅力を引き出すのが、これからの楽しい作業になる。
(写真撮影:光齋昇馬(A~F)、佐藤勝也)
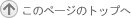
本サイトに掲載されている画像・文章等、全ての内容の無断転載・引用を禁止します。
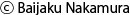
http://www.baijaku.com
| 












